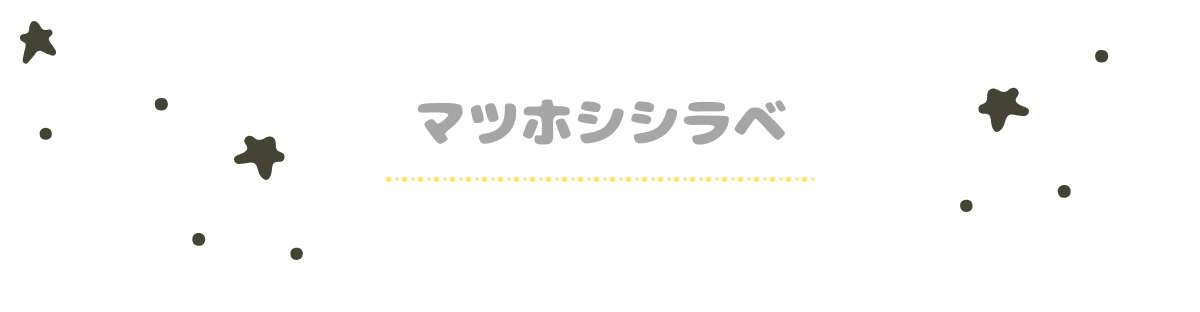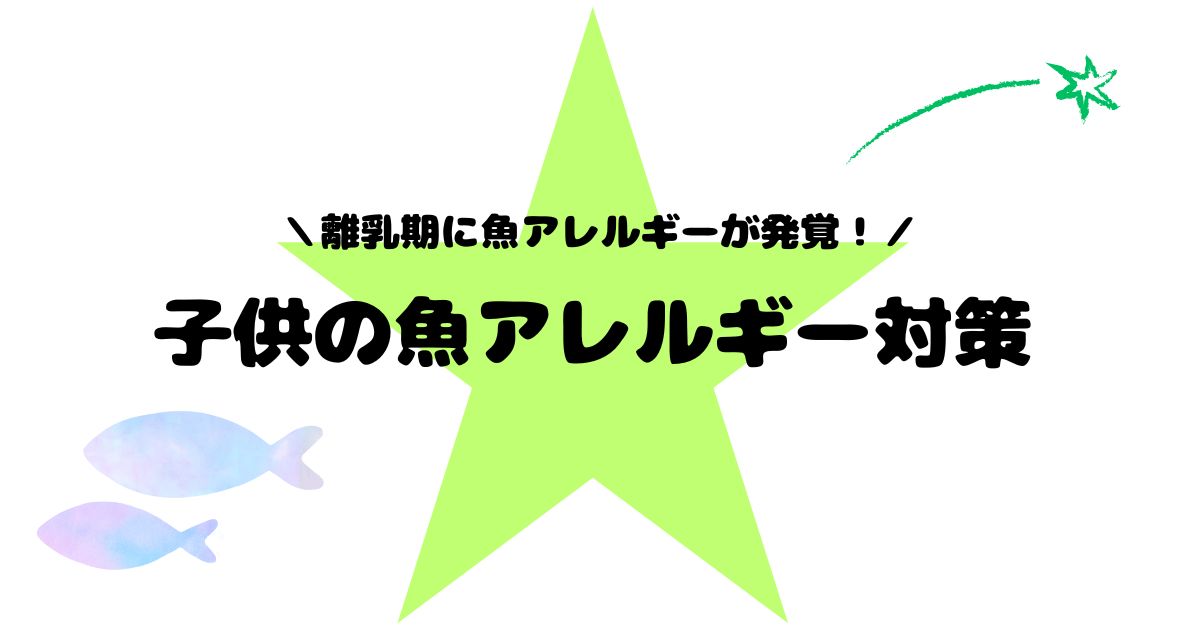今ではアレルギーをもつ人は、3人に1人と言われる時代。
大人になってから、突然アレルギーを発症することも珍しくはないでしょう。
我が家の次男は離乳食が始まった頃から、いろいろな食物アレルギーがあり、小学生になった今も魚アレルギーだけは改善していません。
5大アレルゲンなんて言葉をよく耳にしますが、食物アレルギーは多岐にわたりますね。
- 食事で気を付けることは?
- 魚アレルギーは治るのか?
- 園生活や学校生活は?
今回の記事では、魚アレルギーの子供をもつ経験を含めてお話していきます!参考になることがあれば嬉しいです^^
この記事でわかること
子供が魚アレルギーで学んだこと
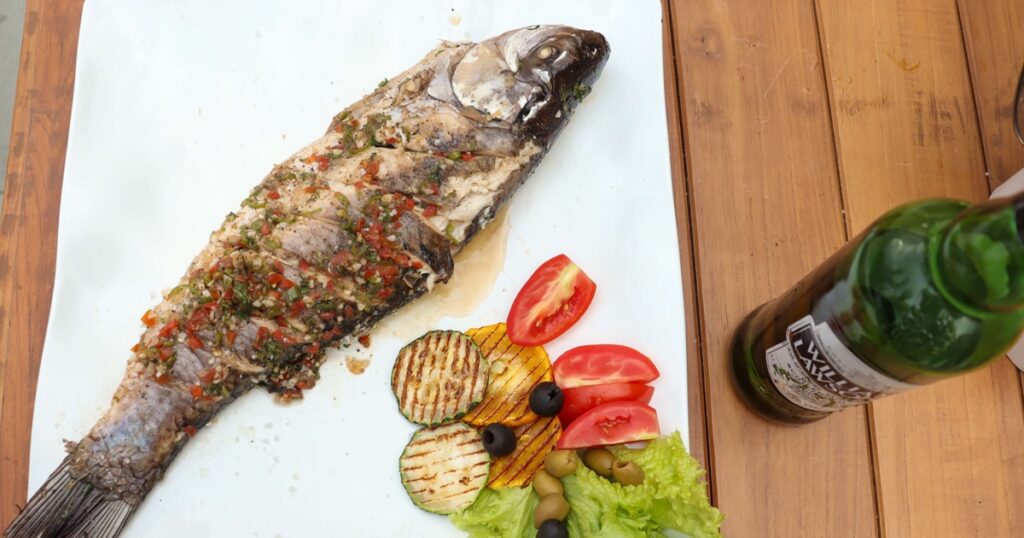
アレルギーの症状は人それぞれで、同じアレルギーでも軽い症状や重い症状と差があります。
実際にアレルギー反応が出るときは、しっかり観察することで気づけることも多いです。
次男の魚アレルギーから学んだことを含めて、まず魚アレルギーの症状からみていきましょう!
なんで食物アレルギーが起こるの?
人間は体の中に細菌やウイルスなどが入り込むと熱が出たり、咳や鼻水などの反応を起こす、それが免疫です。
免疫とは?
病気から免れるために、体を守る仕組みのこと
つまり体に害のあるものを排除しようとする
食物アレルギーはこの免疫の機能が、特定の食べ物に対して「害があるぞー!排除しようー!」と反応し、症状を引き起こします。
ただ食物アレルギーといっても、口から体内に入ったことで症状がでることに限定されません。
吸い込んだり、皮膚に触れたり、駐車から体内に入ったときもアレルギー反応が起こることがあります。
食物アレルギーの症状
アレルギー症状は人によって出かたはさまざま。
- 皮膚症状(湿疹、痒み、蕁麻疹など)
- 呼吸器症状(息苦しさ、咳など)
- 消化器症状(腹痛、嘔吐、下痢など)
- 目・鼻・口内などの粘膜に症状がでることもある
軽度なこともあれば、重度な症状の場合もあります。
アナフィラキシーとは?
アレルギー反応でも、複数の症状が全身に出現した状態
生命の危機にかかわるので注意が必要
アナフィラキシーの症状は短時間で進行するため、適切な対応が必要です。
魚アレルギー
魚アレルギーは、魚に含まれるたんぱく質「パルブアルブミン」や「コラーゲン」が原因で、アレルギー症状が起こります。
もし血液検査で一つの魚にアレルギーがあると判明したら、他の魚でもアレルギーを起こす可能性があります。
含有量は魚によって違いがあり、白身や赤身などでは判断できない
魚アレルギーの他にも、魚でアレルギーのような症状を起こす場合があります。
- ヒスタミン中毒
- アニサキスアレルギー
ヒスタミン中毒は、魚に含まれるヒスタミンに対してアレルギーが起こるため、魚アレルギーとは異なります。
アニサキスアレルギーは、アニサキスが死んでいてもアレルギーを起こす場合がある
アニサキスアレルギーは、生きたアニサキスを摂取して起こるアニサキス症とは別物です。
アレルゲンはどの魚?一切食べられない?
魚アレルギーの症状として、一概に出やすい魚はコレ!と言えないところが、判断が難しいところ。
アレルゲンとなる、パルブアルブミンやコラーゲンの含有量は魚によって違いがあります。
我が家の次男を例に、魚を食べた時のアレルギー症状の出かたをみてみましょう。
次男のアレルギー症状の出かたの例
- さけ・・・焼き魚は数口で腹痛・咽頭症状
- しらす・・・咽頭症状が出るときと、出ないときがある
- かれい・・・一切れ食べても症状が出ない
次男はアレルギーが発覚してからこれまで、症状が出たら食べるのをやめる。
症状が出なければ食べても良いと、かかりつけ医で言われてきました。
練り物や缶詰は食べられることが多い!
焼き魚など魚そのものを調理したものは症状が出やすい
美味しそうだから食べたいけど、アレルギーが出るから食べないという選択もしばしば。
前は大丈夫だったのに今回はアレルギー症状がでた!ということもあるので、食べる時は注意深く観察しながら食べることが重要です。
魚アレルギーの検査や食事のとり方
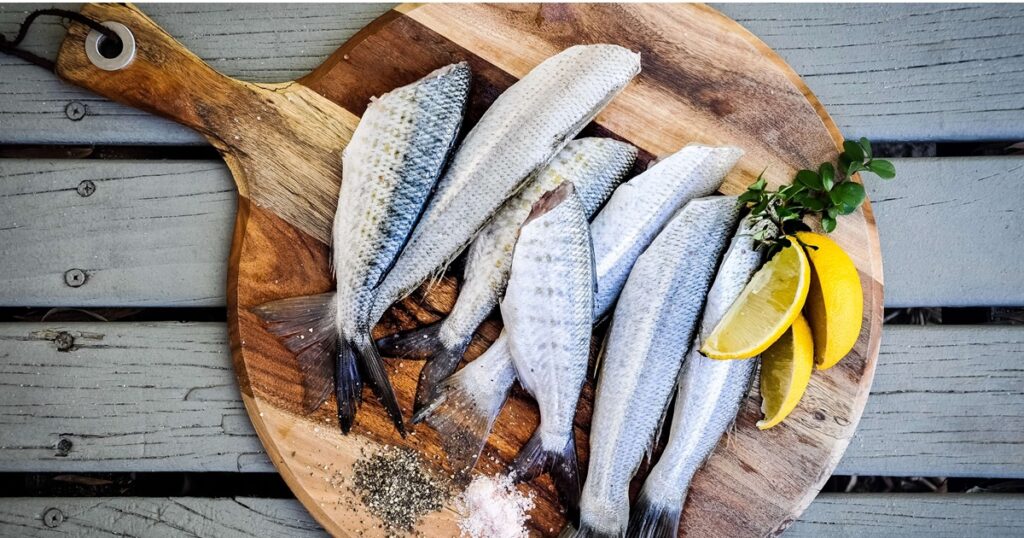
アレルギーの原因となる食物を避けることで、アレルギー症状が出ることは避けられます。
魚アレルギーの場合、どうしても食べる必要がある!ということは少ないでしょう。
しかし食べても良いものとダメなものを知っているだけで、食生活も過ごしやすくなりますよ!
血液検査
アレルギーの血液検査は、確定検査です。
血液検査だけで診断できるわけではなく、アレルギー症状が出た経緯を含めて、検査や診断がされます。
一度の採血で検査できる項目は、病院によって異なるので確認しましょう!
検査後にアレルギーが確認された場合は、食生活の注意などを相談しましょう。
原因となる魚の成分を知ることで、食べる時に注意を払ったり、避けるべきか対策しやすくなります。
食事のとり方
魚アレルギーがわかったら、まずはかかりつけ医に相談するのがベスト◎
アレルギー反応を防ぐには、魚の摂取を避けることが効果的。
しかしすべての魚に対してアレルギーが出ない場合もあり、加工されているものには反応しないこともあります。
- 魚が原料の出汁
- 加工食品(ちくわやはんぺんなど)
- 缶詰(サバやツナなど)
上記のものは除去の必要はないこともあります◎
我が家の次男は、学校などでは除去、家庭では様子をみて症状が出なければ与えても良いということになっています。
離乳期に魚アレルギーが発覚したら

早期にアレルギーが発覚する場合、離乳食がスタートしたあとに知ることが多いかもしれません。
離乳食を始める時は情報を参考にすすめていく方も多いと思いますが、我が家もよく育児本などを頼りにしていました。
情報とは別で、その子がアレルギーがどうかは観察しながらすすめていくのが重要ですよ!
離乳食と魚アレルギー
魚は栄養価も高く、離乳期から食べすすめることが多い食材です。
どんな食材でも同様に、離乳食で初めて与えるものは少量から様子を見るようにします。
魚を与えたあと、アレルギー反応がないか確認!
すぐに症状がでることもあれば、時間の経過とともに症状がでることもあります。
次男が魚アレルギーだと発覚したのは離乳食の中期でしたが、当時のかかりつけ医にこう言われました。
魚を食べなくても生きていかれる。だから食べられるものを食べていればいい
魚以外にも食物アレルギーが発覚していたため、私も初めてのことで不安でしたが、その通りだなとホッとしたのを覚えています^^
魚以外での栄養補給
魚アレルギーがあって、食生活から魚を除去したときに不足しやすい栄養素はなんでしょうか?
- たんぱく質
- ビタミンD
- 多価不飽和脂肪酸(DHA、EPA)
- カルシウム
などなど・・・あげたらキリがないかもしれない^^;
しかし代わりに食べられるものは多くあるので、摂り入れやすいものを食事に加えていきましょう。
お肉をメインのおかずにしたり、ビタミンDやカルシウムが不足しないように卵黄やきのこ類などを摂り入れるといいですね。
園生活や学校生活は?
居住する地域や、入園先や入学先によって、アレルギー対応はさまざま。
アレルギーがある場合は、事前に入園先・入学先によく確認しておくことをおすすめします!
ここでは次男がどうだったかを例にして紹介しますよ^^
アレルギーの種類にもよりますが、次男の場合は1年に1回の栄養相談。
栄養相談の回数や頻度は、地域や食物アレルギーの種類によっても異なります。
学校は食物アレルギーの種類によって対応が異なるので、確認するようにしましょう。
次男の場合は代替食を持参することになっていますが、誤って配膳されないように学校で確認してもらいます。
万が一アレルギー症状が出てしまったという事がないように、信頼をもって家庭と学校で連携したいですね。
魚アレルギーは治るのか
アレルギーの中には成長と共に治るもの、突然発症するものとさまざま。
魚アレルギーは、年齢を重ねるうちに症状が和らぐこともありますが、完全に治ることは少ないと言われています。
そのため子供の頃に発覚すると、大人になっても症状が続くことが多いのが魚アレルギー!
かかりつけ医に相談して、どのような対策が必要か知っておくことで食生活も安心できるでしょう。
実際に食べたり触ったりしてみて、身体に反応があるなら避ければいい
問題なければ食べてもいいし、触っても大丈夫
次男はそう言われているため、家庭での食事は完全除去ではありませんが、食生活に観察はつきもの。
本人が”自分は〇〇を食べるとアレルギー反応が起こる”という意識をもって食事ができるようになった今は、声をかけることで十分気を付けることができています。
魚アレルギーの子供への対策を考えるまとめ
子供の食物アレルギーがわかると、食事の準備以外にも気がかりなことは増えるでしょう。
生活の中で気を付けることや、安心につながる情報を知ることで、少し肩の力を抜くことができるかもしれません。
最後までご覧くださりありがとうござました。